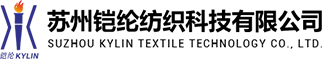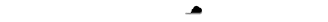シリコーン難燃システム
シリコンシリーズの新しい難燃改質方法には、シリコーン系難燃剤と無機シリコン系難燃剤があります。シリコーン系難燃剤は主にシロキサン化合物です。例えば、シリコーン系難燃剤アクリロニトリル繊維を使用した難燃ポリマーは、燃焼時に有毒ガスが発生せず、溶滴が発生しないという利点があります。現在、無機ケイ素系難燃剤は主にポリアミド/無機粘土ナノ複合材料の形態を採用しています。外国では、ポリエステル材料の物理的および機械的特性および燃焼特性を変更するために、ポリエステルの重合プロセスまたは紡糸溶融物にナノ層ケイ酸塩材料を添加することも研究されている。中国科学院化学研究所もこの分野で研究活動を行っており、一定の成果を上げている。

無機難燃剤の超微粒子は、今日の難燃技術の開発においてホットスポットとなっています。固体難燃剤を物理的または化学的手法を用いて1~100nmの粒子に分散させる方法をナノ難燃技術と呼びます。物理的方法としては、蒸発凝縮法や機械的粉砕法などが挙げられる。化学的方法には、気相反応法と液相反応法とがあります。たとえば、三酸化アンチモンは排ガス反応蒸発領域のプラズマ アークを通過して蒸発し、その後冷却のために凝縮チャンバーに入り、0.275 nm の三酸化アンチモン粒子を得ることができます。超微粒子難燃剤処理技術は、難燃剤の効率を向上させ、難燃剤の量を減らすだけでなく、難燃剤の耐煙性、耐候性、着色性の向上にも大きな効果をもたらします。近年、海外で開発されたコロイド状三酸化アンチモンは、粒径が小さい(100nm以下)、分散しやすい、色濃度が低いなどの特徴を持ち、難燃性繊維の実用化において良好な成果を上げています。
マイクロカプセル技術
マイクロカプセル技術は、水酸化アルミニウムや水酸化マグネシウムをシランやチタン酸塩で表面処理するなど、難燃性粒子を包み込む技術です。または、無機担体の空隙に難燃剤を吸収してハニカムマイクロカプセルを形成する。難燃剤は、難燃剤とポリマーの相溶性を改善することができる。シラン分子とチタン酸塩分子は、水酸化アルミニウムと水酸化マグネシウム粒子の表面に「分子膜層」を形成し、難燃剤とポリマーの間に「架橋結合」が形成されます。ケイ酸塩とシリコーン樹脂を使用することで、熱により分解しやすい有機系難燃剤をしっかりと保護することができ、難燃剤の熱安定性を効果的に向上させることができます。赤リンやポリリン酸アンモニウムなどの難燃剤のマイクロカプセル化については、国内外で多くの研究が行われている。マイクロカプセル化された赤リンとポリアミドのブレンド紡糸により、自己消火性を備えた難燃性ポリアミド繊維も得られます。カプセル化されたポリリン酸アンモニウムは、ポリプロピレン繊維の難燃性にも使用できます。
複合技術
材料の難燃処理中に、特定の難燃剤を同時に使用すると、優れた相乗効果が得られ、より理想的な難燃効果が得られることが判明しました。例えば、リン+ハロゲン、アンチモン+ハロゲン、リン+窒素、リン+結晶水化合物などです。この配合方法を配合技術といいます。ハロゲン・リン・ケイ素化合物を複合塗布すると、より優れた難燃効果が得られ、ハロゲン、リン、ケイ素の難燃相乗効果が得られます。高温では、ハロゲンとリンは炭素の形成を促進し、シリコンはこれらの炭素層の熱安定性を高めます。シランの代わりにシロキサンを使用すると、2 つのリン元素間の難燃剤の相乗効果がさらに強化されます。
合成繊維難燃剤開発の方向性
合成繊維の難燃技術の開発は、難燃効率を向上させながら、難燃性常温染色ポリエステル繊維などの他の特性を同時に備えた多機能化の方向に開発する必要があります。 ;繊維内の難燃剤の相溶性と混合均一性を向上させます。繊維の難燃改質などにおける新しい難燃システムの応用により、難燃繊維の工業化の市場見通しは非常に広範になります。
機能統合
難燃剤の機能配合は新たな開発トレンドとなっており、世界各国で二機能・多機能難燃剤の開発が進められています。複合材料を添加することにより、難燃性帯電防止または難燃性の容易な染色、難燃性および抗菌性の二重の機能および多用途性を発揮できることが期待されており、例えば、帯電防止性難燃剤とポリエステルチップとの混合紡糸の使用が挙げられる。帯電防止難燃性ポリエステル繊維。現在、ヨーロッパ、アメリカ、日本などの国々では、水酸化アルミニウム、シリカ、ホウ酸亜鉛などの難燃・発煙機能を有する無機物質や三酸化アンチモンなどの無機複合難燃剤が生産されています。難燃性繊維をフッ素で処理すると、繊維の難燃性の耐久性が向上するだけでなく、繊維の防水性能も効果的に向上します。
























 Email: [email protected]
Email: [email protected] Tel: +86-512-63221899
Tel: +86-512-63221899